”「子なるもの」と「母なるもの」”
この人見知りの基盤にあるのは、母子の分離と合体の、相反的なゆれ動きである。
そのくりかえしを通して子は母から自立してゆく。
人見知りを検討するにあたって、それぞれ個として分離し自立したあとの、母と子をおもいうかべてはならない。
まだ一歳未満の幼い子供の心のなかでは、母は個としての母ではなく「母なるもの」であり、個も子としての子ではなく「子なるもの」である。
あえて「子なるもの」という聞きなれない言葉をつかったのは、それぞれ個としての母と子の関係でとらえると、子は母に対して完全に無力で依存的な存在となるからである。
しかし、子の心的世界ではそうではない。この世界は、空腹の泣き声という呪文を唱えれば乳首が摩訶不思議にもどこからからか飛んでくるオバケのQちゃん的世界である。
「母なるもの」は「子なるもの」の分身ですらあり、延長ですらある。
現実には無力で依存的ではあるが、その心は万能感にみちている。
たとえ裸の王様であっても王様であることにかわりない。
と同時に、たとえ「子なるもの」の分身・延長であっても、母子分離とともに「母なるもの」は「子なるもの」にとって不思議な力をもった畏怖すべき存在となる。
よくしたもので、何の不思議な力ももちあわせない個としての母も、本能的に「母なるもの」へと変身し、オバケのQちゃんを見守り、ささえ、奉仕する存在となる。
ここでも「子なるもの」は「母なるもの」の分身・延長であるが、その分身・延長は単なる無力な存在ではなく、「母なるもの」にとって王様でもあるのだ。
この心的世界では「母なるもの」も「子なるもの」も対等だ。
この心的世界において対等の力を賦与するのは、生後間もない時期での「母なるもの」と「子なるもの」との未分・一体の混然態である。
この混然態から「母なるもの」と「子なるもの」の分離を示せば、図6のようになる。
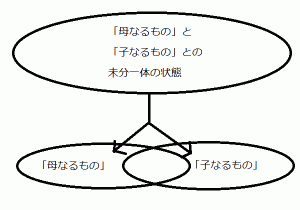
図6
分離はおのずと「子なるもの」に、個としての意識をうながす。
しかし、「子なるもの」の意識は根強いものである。
おそらくこのような意識は、さらには未分・一体の混然態への憧れは成人してもけっして消えることがないほどに根深いものである。
だから分離がはじまっても、乳幼児は接近してくる個としての見知らぬ人に「母なるもの」を見出そうとする。
だが相手はそうではないとわかる。
そのとき乳幼児が感じ取るのは、私たちが対人関係で感じとる「間」と全く同質のものであろう。
「間」を感じたとき乳幼児は、なにを思うのか。相手が祖母だと知って、はにかみながらもその胸にだかれてはしゃぐ、誇り高い喜びを想起するなら、分離と合体のはざまである「間」の意識のなかには、「母なるもの」と「子なるもの」との未分・一体への思いが潜んでいるのだといっていいであろう。
こうみてくると、人見知りにも「間」をめぐる「自」と「他」の三項図式が成立しているのがわかる。
そして「間」の意識には「自」と「他」の未分・一体という、全ての人間がそこからでてそこにかえる、心の故郷への思い、フロイトのいう大洋的感情が潜在しているといっていいのではなかろうか。
ついでに若干のべておくが、分離とともに個としての自分の意識が形成されてゆき、それと同時に個としての他人を「見知る」ようになってゆく。
先の対人恐怖症例の親しく話しかける見知らぬ他人とは、個としての他人である。
そのような個としての存在を体現したものが、「父なる」存在である。
だから父親とは、いささか煙ったい存在にもなる。
また、それゆえ父親は個の確立と規範性の形成にとって不可欠な存在でもあるのだ。
以上は、人見知りの問題にからませて、精神分析学の見方を著者なりの言葉で述べたものである。
精神分析学の見方を自己流に我田引水したとの謗りを、その方面の専門家から受けないとは限らないが、教条主義は著者のもっとも嫌うところである。
ともあれ、ここでいいたいのは、人見知りが乳幼児心性に由来する根深い現象だということである。
その点を知っていただくだけでも、このような考察の意義は十分にあったと思われる。
※参考文献:対人恐怖 内沼幸雄著
